
ペーパーってやっててどんな意味がある?教え方が難しくって叱ってしまう…
そんな疑問に対して、私が現時点で実践しているコツをブログにしました。
(感じたことは、この記事で常にアップデートしていく予定です)
今回は受験の大切な要素の一つ、ペーパーについて。
ペーパーは、受験に必須の勉強内容です。
なぜなら?「質問を聞き取って理解しないと答えられないから」です
「ペーパーがもし出ない学校を受験するとしても、試験を受ける際の読解力は必須だから」とも言えます。
我が家も、家でペーパーを親子で頑張る時間を始めました。
1から始める小学校受験、ですからまずはどうやって親として教えていけば楽しめる??
やりながら答えを探しました。
 独学でデザインとブログを勉強しながら記事執筆中!
独学でデザインとブログを勉強しながら記事執筆中!✔︎只今来年度の小学校受験に向けて、0から子供と学んでいる真っ最中!
年中と0歳を抱えながら、親子で受験のために楽しみながら前進中!
実際来年の小学校受験の結果まで、受験初心者としてブログをお届けします
そこで見えてきたのは「子供にアウトプットさせて腑に落ちているか確かめる」
が重要だと肌で感じてます!

コツを掴みながら「あ!そうか!」と閃かせるのが大切だと親の私も体感中!
・まずは親が途中で口も手も出さない!
・問題を解いた後、どうしてその回答をしたのか?本人に答えさせる
・回答を親は言わずに導いて本人に「ひらめき」を与える
・「もっと速く答えを出すコツ知りたい?」と面白味を与え+αのやり方を伝える
・その上で再度類似問題をやらせてみて「できた!」を積み重ねていく
ではその内容についてお伝えしていきます。
私の大好きな基礎を教えてくれる本です
子供のペーパー実力の伸ばし方は、親も超重要!
小学校受験は、色んな項目が各学校であり、
・巧緻性
・集団行動
・体操
・面談
といった項目がズラズラと並びます。

めっちゃ項目多いな…

逆を言うと、これらが身につくからこそ子供の土台がしっかりすると思うんだ!
子供の土台がしっかりとすると感じたきっかけは、
筆者のきなこが実際、公園でとある女の子たちに会った経験から。
「小学校受験っていいのかもしれない」と感じたある出来事

小学生の女の子2人が、ふと娘に
「鬼ごっこして遊びませんか?」と誘ってくれました。
当時2歳の娘は「やりたーい!」と言って、1人で走って滑り台に行ってしまいました。
(そもそものルールをわかってない2歳の自由人ww)
だけど、その状況を理解して2人は優しく「大丈夫です^^」と言いブランコに乗り始めました。
中々見かけないすごくしっかりした子達だったので「おうちはこの辺なの?」と言う話しかけから、色々仲良く会話をして行った結果「とある人気私立女子校」の女の子達だということがわかりました。

当時の私は、その女子校が皆憧れる学校とは知る由もなく、会話していました(笑)
とにかく会話していてしっかりとして落ち着いているけど、作られた感じではなく自然体。
その2人とはその後会っていませんが、近所の公園で会って一番覚えている2人です。

あの私立の女の子達みたいに、娘もなって欲しいなぁ〜
くらいに思っていたのですが、その印象がとても強いまま「今」に至ります。
実際に「小学校受験をする」という決断をし、色々と課題を進めていく結果、子供のしっかりとした土台は、親が共に築いてあげなきゃなんだなぁって感じています。
親は先生のように教える「プロ」じゃないから、親も一緒に成長!

ではそんな子達を目指して、実際に受験勉強を始めてみて感じたことです。

まだ親子で取り組み始めてまも無いんですけどね!
特にペーパーに関しては教え方を間違えたら子供は混乱をきたす上に、コツをつかめないまま試験中も制限時間が来てしまう!と痛感しました。
「プロ!」とまでは行かなくても【確実にスピード回答していくコツ】を伝えなくては意味がないと感じました。
とはいえ、先生方に「家で宿題をやってきてください」と言われた際に、
・それを聞いて回答するのが子
なので、1人でやらせる事なんてもちろんできません。
ましてや素人の親が教えるなんて、中々の重大責任…
先生のように「プロ」な教え方は中々難しい!!
ただ取り組んでいくうちに、このやり方であれば一緒に取り組めるなと感じました!
・まずは親が途中で口も手も出さない!
・問題を解いた後、どうしてその回答をしたのか?本人に答えさせる
・回答を親は言わずに導いて本人に「ひらめき」を与える
・「もっと速く答えを出すコツ知りたい?」と面白味を与え+αのやり方を伝える
・その上で再度類似問題をやらせてみて「できた!」を積み重ねていく
①まずは親が途中で口も手も出さない!

生まれてまだ4年、5年、6年しか経ってない我が子。
そんなすぐに、大人のようにスラスラと解けるわけもなく…
ですが、結果を出したいのは親であるために、つい、

なんでわからないの?ちょ…待てよ(キムタク)!話聞いてた?!!!
とイライラが募るものです…
自分目線になればなるほど、せっかちである人ほどその感情が爆発するでしょう…

だけどまず!一度、全部子供に回答させていく!
これに尽きると思います。
わかっちゃいるけど、つい口が出てしまうのが親です(笑)

せっかちな皆さん!まずは私と一緒にこらえましょう(笑)
小学校受験は、ある意味「忍耐」が必要と感じました。
「忍耐」は、子育て全般に言えることかもしれませんが!
そして、問題を読むときに「抑揚」をつけて話さないこと!
これを感じました

は?抑揚をつけないってどんな意味?
と思うかもしれません。
ここでいう「抑揚」は、
聞いている子供の目線に合わせて、わかりやすく問題を喋らないという意味です。
例えば…

「左の四角の中にあるリンゴと、右の四角の中にあるりんごを、足したら10になるようにそれぞれ線を引きなさい」
という設問の時に「左の四角の中にある〜!」といった部分を声をあげて強調して、伝わるように言ってしまいがちになるのが親です。
でもそこはグッとこらえて、抑揚をつけずにさらりと読むのがコツかなと感じます。

多分試験会場では、そんな優しく読んでくれる先生はいないと思うからです!
子供がきちんと、聞き耳を立てて「よし聞くぞ!!」という体勢になっていないと、「聞き取り力」は伸びない!
と我が子をみて感じたのです。
そう感じた理由は、都内ではとても受験結果の実績がある教室に体験に行き、
先生が感情の起伏なく、突然ペーパーを始めているのを見て、

一見キツく感じるけど、確かに感情を前面に出した試験会場なんて当日ないよな…
と体感したからです。
②どうしてその回答をしたのか?本人に答えさせる

そして、子供が鉛筆をおいたらようやく話しかけます。

これはどうしてその答えにしたの??
プラスもマイナスも感じさせずに、ただ問うのです!

この「答えさせる」を繰り返し、繰り返し、積み重ねていく事で「伝える事」が確実に上達していくと感じています。
③回答を親は言わずに導いて本人に「ひらめき」を与える

そして正解していればハイタッチ!!(我が家のやり方)
もし間違えていたときは、
「再度問題を読み直してあげる」
初めてここで「抑揚」をつけて、親側も伝わるように問題を話します。
1度目と違って、伝わってほしい!と言う気持ちを込めて読むのです。

実際の試験会場では「優しく抑揚をつけて伝わりやすく読んでくれることはない」と思って挑む方が、今後【話の聞き取り力】も強くなると思います!
そこでひらめく時は「あ!」と自分で気付きます。
もしくは、②の項目で子供自身が「なぜその解答にしたか?」を答えている最中に「あれ??」と間違いに自ら気づくことも多いです!

教えるのはカンタン、導いてひらめかせるのは難関!
④「もっと速く答えを出すコツ知りたい?」と面白味を与え+αのやり方を伝える

そして、小学校受験ではどうやら「制限時間」が設けられていたりして、スピーディーな解答も求められます。
そのため、丁寧に解答するのも大事ですがプラスして「早く」解答する
ということも大切なポイントだと感じました。
そんな時私は

ねぇねぇ、今全部合ってた答えをもっと早く!書ける方法、知りたくない??
とめっちゃあおります(笑)
必ず「知りたい!」と言うので、そこで【コツを伝えること】がポイントです!
例をあげると

(見えづらかったらすみません)
こちらのペーパー。
足したら「13」になるように線を引きなさいという質問内容
我が子は、1、2、3、4、5…と何度も数えなおしていました。
そんな時に

「数が多いものは何度も数え直さなくていいように、横に数字を書いておけばいいよ!
と伝えて、実際に「数が多いもの」には数字を書いてあげます。
(画像は私が、数の多いものだけに数字を入れてあげました)
そうすると、時間短縮で仕上げられます。

こういった、ちょっとしたコツって未就学児は意外と知らなかったりします。
大人は知っていていも、子供は知らないことが多いです。
「とにかく子供目線になる!」のがポイントかなぁと感じています
⑤その上で再度類似問題をやらせてみて「できた!」を積み重ねていく
④で腑に落ちているようだったら、似た問題をすぐに実際にやらせてみます。

これは実際に娘が解答したものです。
少し質問内容が違って「足したら13にならないように線を引く」内容ですが、やることは基本同じ!
さっき伝えた通りに数字を一生懸命書いていたので、あとは得意の足し算で正解していました。

ただ、この復習をもう一度やってみないと忘れてるかもしれないから、確認の為に明日リトライだw
ちょっとしたコツの差で、解答時間も早くなるのかなと感じました。
オススメドリルは、私は「こぐま会」です
まとめ

ペーパーをやっていくうちに感じた【親でもできるペーパーで寄り添う方法について】シェアさせていただきました。
プロではないからこそ、意外に難しい「教える」ということ。
私の母は元中学校の教師ということもあり、アドバイスを聞きながら、かつどうすれば娘のモチベーションを維持しながら楽しんでもらえるか?
とモットーに頑張っている最中です!
・まずは親が途中で口も手も出さない!
・問題を解いた後、どうしてその回答をしたのか?本人に答えさせる
・回答を親は言わずに導いて本人に「ひらめき」を与える
・「もっと速く答えを出すコツ知りたい?」と面白味を与え+αのやり方を伝える
・その上で再度類似問題をやらせてみて「できた!」を積み重ねていく
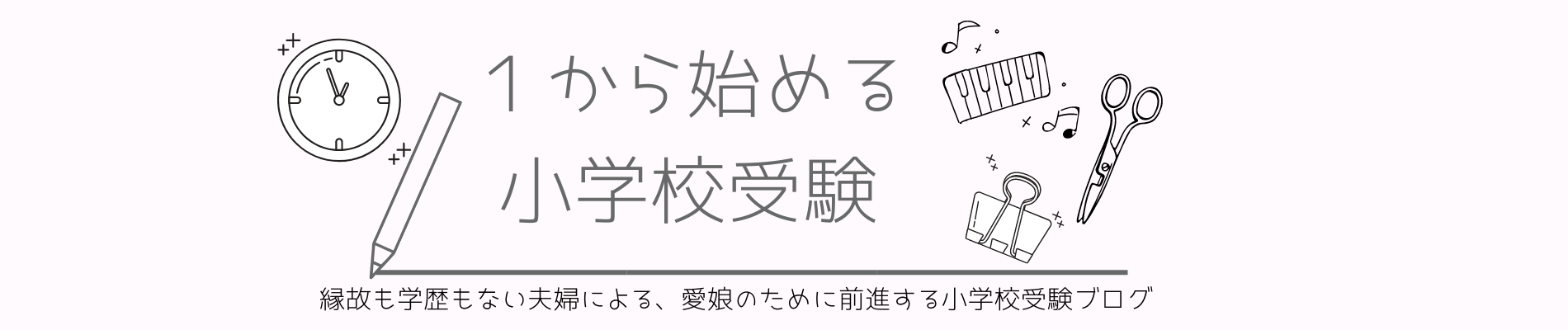

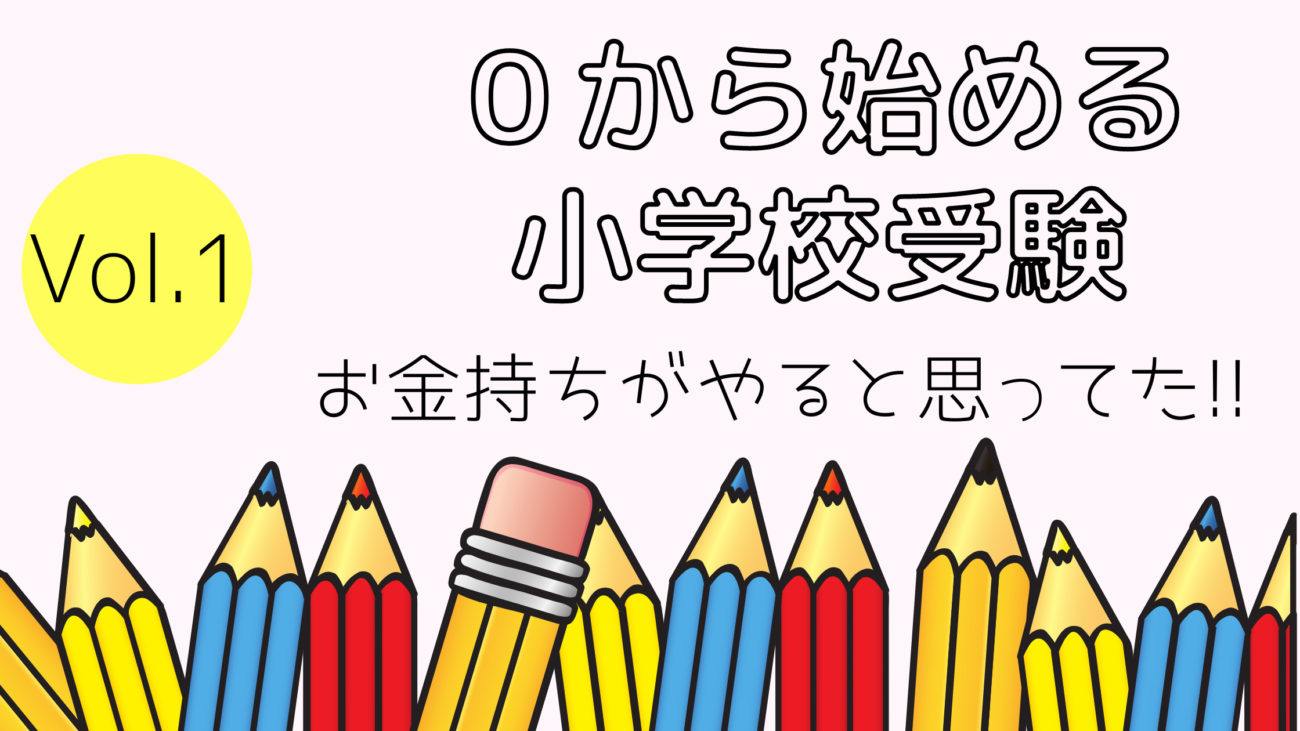
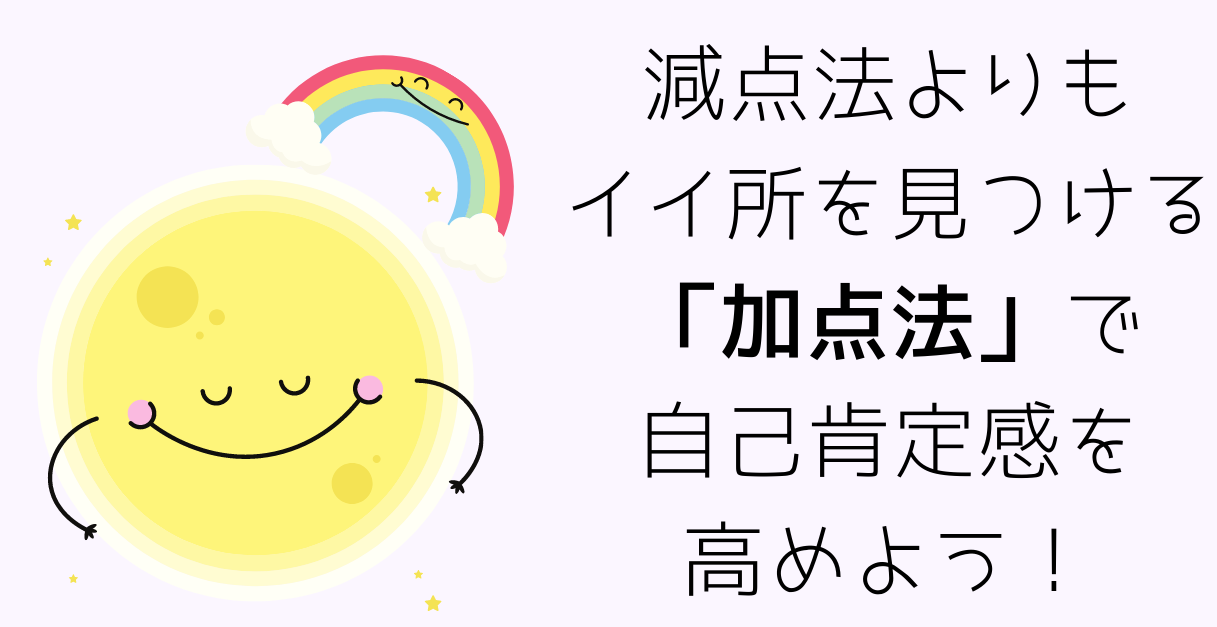
コメント